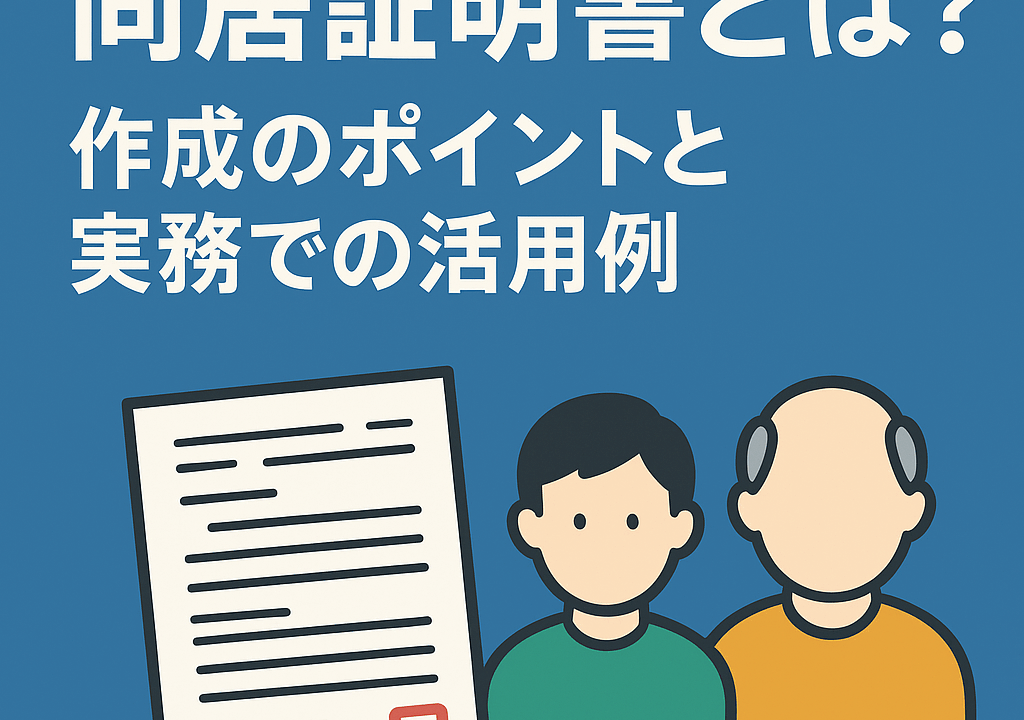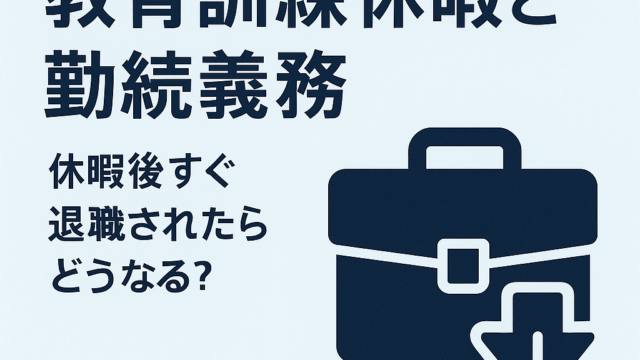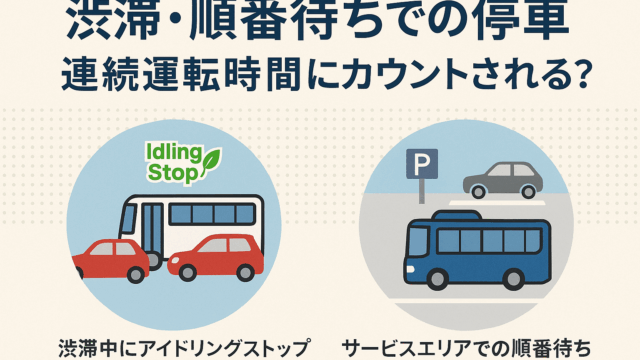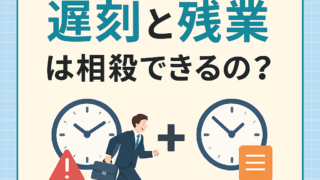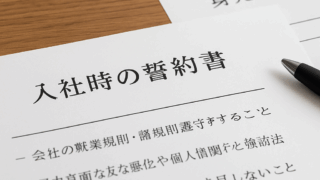企業の労務担当者や社会保険担当者にとって、「同居証明書」は意外と使用頻度の高い書類のひとつです。
今回は、同居証明書が必要となる場面と、作成時の注意点をわかりやすく解説します。
1. 同居証明書とは?
同居証明書とは、従業員と親族が同じ住所に住んでいることを会社が証明する書類です。
例えば、次のような場面で提出を求められることがあります。
- 社会保険の被扶養者認定(特に住民票上の住所が異なる場合)
- 健康保険組合や協会けんぽへの申請
- 企業独自の家族手当や住宅手当の申請
同居の事実を証明することで、扶養認定や手当の支給を受けられる場合があります。
2. 同居証明書の主な記載事項
アップロードされたひな型の内容を整理すると、以下の項目が含まれています。
- 被保険者(従業員)の氏名・生年月日・住所
- 同居親族の氏名・続柄・生年月日・住所
- 同居開始日
- 住民票上の住所が異なる理由(必要に応じて)
- 会社名・所在地・代表印
特に注意したいのは、住民票の住所が異なる場合の理由記載です。
たとえば「二世帯住宅で住民票は分けている」「住民票移動の手続き中」など、合理的な理由を明記します。
3. 実務での提出例
【事例】扶養認定で同居証明書を提出するケース
状況
従業員Aさんの母親を健康保険の扶養に入れる手続きを進めています。
実際には同居しているものの、母親は住民票を実家に残したままです。
対応
健康保険組合から「同居証明書」の提出を求められたため、会社が以下の書類を作成しました。
- 被保険者(Aさん)の情報
- 同居している母親の情報
- 同居開始日
- 「住民票上は別住所だが、実際には同居している」旨の理由
証明書を添付したことで、無事に扶養認定が承認されました。
4. 作成・提出時の注意点
- 記載内容は事実に基づくこと(虚偽記載は法的トラブルの原因になります)
- 代表印の押印が求められる場合があるため、社内の押印ルールを確認する
- 社内で控えを保管しておくと、将来の確認にも便利です
まとめ
同居証明書は、社会保険や手当の申請において事実確認を行うための重要書類です。
社内でフォーマットを整備しておくと、扶養認定や手当申請をスムーズに進められます。
✅ 初回相談無料|社会保険や扶養手続きのご相談はこちら